EDになりやすい人の特徴!治るきっかけにつながる予防・対策方法
2026年1月9日

EDには様々な原因が存在しますが、適切な対処法を知ることで改善できる可能性が高いです。
この記事では、EDになりやすい人の共通点や、治るきっかけなど、どのような行動や対策をすればEDの予防や治るきっかけにつながるのかを解説します。
EDになりやすい人の生活習慣や特徴
EDになりやすい人の性格や年齢、生活習慣についてまとめました。
もし自分が該当している場合は、事前に対策を行うとEDの予防につながります。
EDになりやすい人の性格・年齢の特徴
EDになりやすい人の傾向としては、性格的に不安定である場合や、40代以降の男性に多くみられます。
EDになりやすい人の特徴として、日常的にストレスを溜めやすい人が多い傾向にあります。
仕事や人間関係などで緊張状態が続くと、自律神経のバランスが乱れ、勃起に必要な神経伝達がうまく働かなくなってしまいます。
とくに、ネガティブ思考になりやすい人や他人の評価を気にしすぎる人、感情を外に出すのが苦手で我慢を重ねやすい人は心的EDに繋がりやすいため注意が必要です
EDを発症しやすい年代は40歳以上の男性が中心です。
40代以降は加齢とともに男性ホルモン(テストステロン)の分泌量が徐々に低下し、血管や神経の働きも弱まるため、結果として勃起しにくくなる傾向があります。
また、動脈硬化や血流低下が進みやすい年齢でもあるため、性的な刺激を受けたとしても十分な血液が陰茎に届かずに勃起が維持できないケースが増えます。
生活習慣の乱れがEDの原因になることもある
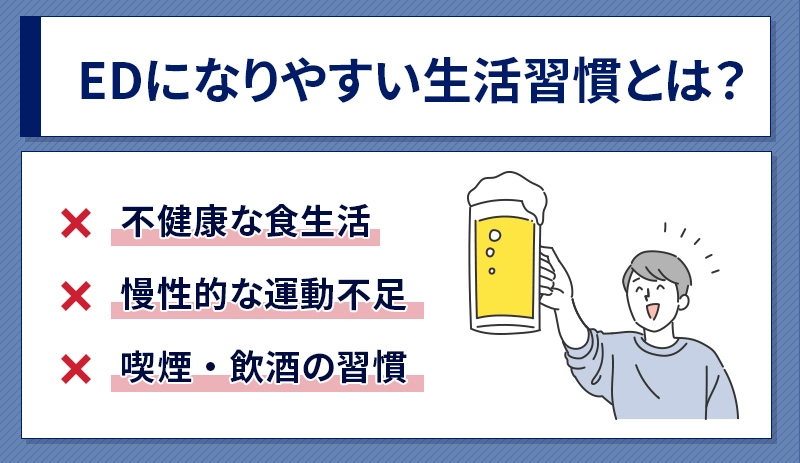
生活習慣が乱れている人は、血管障害やホルモンバランスの乱れが起きやすいためEDになりやすいです。
EDになりやすい生活習慣について、一つずつ解説します。
EDになりやすい生活習慣
- 運動習慣がない
- 食生活が乱れている
- 喫煙習慣がある
- 過度に飲酒をする人
- 持病がある人
運動習慣が不足している場合、全身および下半身の血管内皮機能が低下し、勃起に必要な血流の供給を妨げるため、EDを発症する原因となります。
運動習慣のない男性は、週に150分以上の有酸素運動を行う男性と比較して、EDを発症するリスクが約40〜60%高くなることが示されています。
参考:「Effect of different physical activities on erectile dysfunction in adult men (Andrology, 2024)」
食生活が乱れている人は、EDになりやすい傾向があります。血管の健康を損なう食事が続くと、陰茎に十分な血液が届きにくくなり、勃起が起こりにくくなるためです。
EDになりやすい食習慣
- 揚げ物やお菓子が多い食事
→血管が硬くなりやすいマーガリンやショートニングを使った食品、市販の揚げ物やスナック菓子 - 白い炭水化物に偏った食事
→血糖値が急激に上がりやすい白米や白パン、甘いお菓子 - 塩分の摂りすぎ
→ラーメンや加工食品中心の食事は高血圧を招きやすく、血流を悪くする原因に - 肉中心の食生活
→赤身肉やハム・ソーセージを頻繁に食べていると、悪玉コレステロールが増え、血管の働きが低下しやすくなる
血管や血流に負担がかかる食事が習慣化している人ほど、EDを発症しやすくなります。血管の健康を保つためには、外食や加工食品を控えめにし、野菜・魚・豆類などを取り入れたシンプルな食事を意識することが大切です。
喫煙はEDの最も強力なリスク要因の一つです。タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素は血管を収縮させ、勃起に必要な血流を減少させます。喫煙者は非喫煙者と比較して、EDを発症するリスクが約1.51倍〜2倍も高いことが報告されています。
参考:「Smoking and risk of erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis (J Sex Med, 2015)」
アルコールとEDの関係は、飲む量や飲み方によって大きく変わります。
少量のアルコールを摂取すると血管が広がりやすくなり、緊張が和らぐため、短期的には勃起しやすく感じる場合があります。
一方で、飲酒量が増えすぎるとEDへとつながる可能性もあります。アルコールには神経の働きを鈍らせる作用があり、過剰に摂取すると性的刺激が脳から陰茎へうまく伝わらなくなります。
さらに、慢性的な多量飲酒は男性ホルモンであるテストステロンの分泌を抑え、性欲の低下や勃起力の低下につながりやすくなります。
アルコールは少量なら影響が出にくい一方、習慣的な飲みすぎはEDリスクを高める要因になります。飲酒の頻度や量を見直すことは、ED予防の観点でも重要なポイントです。
糖尿病・高血圧・高脂血症・心臓病などの持病がある人は、器質性EDを発症しやすい傾向があります。
これらの病気は血管や神経に慢性的な負担をかけ、勃起に必要な血流や神経の働きを妨げる可能性があります。
生活習慣病や循環器系の持病は、自覚がないままEDにつながるケースが多いため、持病の管理や治療を継続することは、体調だけでなく勃起機能を守るうえでも重要になります。
EDが治るきっかけや予防・改善策を4つの原因別に解説
「メンタルが原因なら解消すれば治るの?」「生活習慣を正せば治る?」「もう手遅れではない?」と考えている人に向けて、EDが起こる主な原因別に、改善の考え方と向き合い方を整理します。
EDは原因によって、「自分で整えられる部分」と「医療のサポートが必要な部分」がはっきり分かれます。
持病がきっかけで起こるEDの改善策
糖尿病・高血圧・心臓病などの持病が原因で起こるEDは、器質性EDに分類されます。
器質性EDは血管や神経そのものに障害が生じているため、自己判断だけで治すのは難しいのが特徴です。
器質性EDを治すために必要なのは、まず持病そのものの治療を安定させることです。病状が改善すると、血流や神経機能が回復し、EDの症状が軽くなる場合があります。
器質性EDが改善につながる主な要因
- 持病の治療継続(糖尿病・高血圧など)
- 医師の判断による薬物治療
- 泌尿器科・ED外来での専門的な評価
ただし、持病がある場合でも、医師の管理下であればED治療薬が使えるケースがあるため、ED治療をしたい場合は主治医や専門医に相談するようにしましょう。
ストレスがきっかけで起こるEDの改善策
強いストレスやプレッシャーが続くことで起こるEDは、心因性EDと呼ばれます。
心因性EDは身体に大きな異常がなくても、緊張や不安がきっかけで発症します。
心因性EDでは、考え方や環境が変わることで改善するケースもあります。たとえば、パートナーとの関係性が落ち着いたり、性行為に対する失敗の不安が軽くなる、刺激が強い自慰行為(オナニー)を止めるなどによって、症状が和らぐことがあります。
心因性EDが治るきっかけ
- 性に関するコミュニケーションの見直し
- プレッシャーを感じない環境づくり
- 専門家(泌尿器科・性機能外来・カウンセラー)への相談
心因性EDは思い込みや考え方を少しずつ変えることで改善しやすい一方で、長期間放っておくとEDの症状が悪化する傾向にあります。
心因性EDの長期化を防ぐためには、クリニックによる早期のED治療を受け、重症化する前に成功体験をすることが重要です。
薬がきっかけで起こるEDの改善策
高血圧やうつ病など、持病の治療薬が原因でEDを発症している場合、その薬を止めたり種類を変更したりするだけでも改善するケースがあります。
この場合、薬の種類や量を調整するだけで改善するケースもあります。
ただし、自己判断で薬を中断することは危険であるため、処方している医師にEDの可能性があることを相談した上で、代替薬や調整の可否を確認するようにしましょう。
複数の要因が混ざって起こるEDの改善策
身体的な原因と精神的な原因が重なっているEDは、混合性EDに分類されます。
年齢とともに増えやすく、「どれが原因か分からない」と感じやすいのが特徴です。
混合性EDへの考え方
- 身体的アプローチ(器質性EDの対策) → 持病の治療や生活習慣の見直し
- 心理的アプローチ(心因性EDの対策) → パートナーとの関係改善、成功体験の積み重ね
もし混合性EDの可能性がある場合、原因が一つではないため、治るきっかけを自分で見つけるのが難しい傾向にあります。
混合性EDの場合は、ED治療薬を使用して性行為の成功体験を積み重ねることで、精神的な負担が少なくなり、EDの改善の鍵になる場合があります。
ただし、持病によってはED治療薬の服用ができない場合もあるため、まずは持病の治療を受けている医師に相談するようにしましょう。
生活習慣を見直しがEDの治るきっかけとなる場合もある
EDの改善や予防において、生活習慣の見直しは基本となる要素です。
とくに軽度から中等度のEDでは、日常の行動が血流やホルモン環境に影響し、症状が和らぐケースがあります。
生活習慣だけでEDが必ず治るわけではありませんが、他の対策や治療の効果を高める土台として重要です。
食事・喫煙・睡眠など日常の生活習慣がEDに与える影響
EDは血流や神経、ホルモンの働きと深く関係しているため、日常の生活習慣の影響を受けやすい症状です。
生活習慣の一つひとつの影響は小さくても、積み重なることでEDの発症や悪化につながるため、できることから生活習慣の改善を始めていきましょう。
これまでに運動習慣がなかった方は、まずは1日10分程度のウォーキングから始め、徐々に運動量を増やしていくことで、EDの改善に繋がります。
過度な長距離走や高強度のサイクリングは逆にEDリスクを高める可能性があるため、適度な運動を心がけましょう。
禁煙によるED改善効果は比較的早く現れることが多く、禁煙後2〜12週間で勃起機能の改善が見られることもあります。
アルコールは日本酒なら1合程度の適量にとどめておくことで、EDが治るきっかけとなります。
睡眠中にはテストステロン分泌が活発になり、特にレム睡眠中には陰茎海綿体への血流が増加します。
そのため、質の良い睡眠を取ることで、ED改善に繋がります。
睡眠の質を改善するための具体策
- 就寝前のリラックスタイムの確保
- 規則正しい睡眠スケジュール
- 寝室環境の整備(温度、騒音、光の管理)
もし睡眠時無呼吸が疑われる場合は、専門医の診断と治療を受けることで、睡眠の質とともに勃起機能も改善する可能性があります。
| 生活習慣分野 | 具体的な改善策 | 期待できる効果 | 実践のコツ |
|---|---|---|---|
| 食事改善 | 地中海式食事法、野菜・果物増量 | 血管機能改善、NO産生促進 | 加工食品削減、魚・オリーブ油増量 |
| 運動習慣 | 週150分の有酸素運動、筋トレ | テストステロン増加、血流改善 | まずは毎日10分のウォーキング |
| 睡眠改善 | 7-8時間の質の良い睡眠 | ホルモンバランス調整 | 就寝時間の規則化、ブルーライト制限 |
| 体重管理 | BMI 25以下の維持 | テストステロン回復、血管機能改善 | 少量ずつの減量(月2kg程度) |
| ストレス管理 | 瞑想、趣味の時間確保 | 自律神経バランス改善 | 毎日5-10分の深呼吸法 |
| 禁煙 | 完全な禁煙 | 血管機能回復 | 禁煙外来の活用 |
| 適正飲酒 | 日本酒1合程度/日 | 緊張緩和(過剰摂取は逆効果) | 週2日以上の休肝日 |
| 骨盤底筋強化 | ケーゲル体操(1日3回) | 勃起維持力向上 | 排尿中断テストで筋肉確認 |
| デジタルデトックス | ポルノ視聴制限、スマホ使用制限 | 脳の報酬系回復 | 就寝前はデジタル機器を避ける |
食生活の改善が血流環境を整える土台になる
食生活は、EDと関係の深い血管の健康に直接影響します。
外食や加工食品が多い食事が続くと、血管に負担がかかり、陰茎への血流が不足しやすくなります。
魚・野菜・豆類・ナッツ類を中心とした食事は、血管の柔軟性を保ちやすく、EDリスクを下げる方向に働きます。特別な食事療法を行う必要はなく、加工食品を減らし、素材に近い食事を増やす意識がEDの改善には重要です。
| 食品・栄養素 | 勃起機能への効果 | 主な含有食品 | 推奨摂取量 |
|---|---|---|---|
| オメガ3脂肪酸 | 血管内皮機能改善、炎症抑制 | 青魚、亜麻仁油、クルミ | 週2-3回の魚料理 |
| リコピン | 血管保護、抗酸化作用 | トマト、スイカ、ピンクグレープフルーツ | 毎日のサラダや料理に |
| フラボノイド | NO産生促進、血管機能改善 | ベリー類、柑橘類、ダークチョコレート | 毎日少量 |
| アルギニン | NO前駆体、血管拡張 | ナッツ類、豆類、魚、赤身肉 | 週3-4回 |
| 亜鉛 | テストステロン産生促進 | 牡蠣、牛肉、カボチャの種 | 1日8-11mg |
特に血流改善に効果的な食品としてニンニク、玉ねぎ、サーモン、ナッツ類、緑黄色野菜などが挙げられます。
これらの食品はNO(一酸化窒素)の産生を促進し、血流の改善や血管拡張の効果が期待できます。
また、亜鉛(牡蠣、牛肉、かぼちゃの種など)やL-アルギニン(豆類、魚、鶏肉など)を含む食品も男性の性機能をサポートするため、EDの予防やEDの改善を考えている人はこれからの食事に取り入れるようにしましょう。
EDは自然に治るとは限らず、生活習慣改善にも限界がある
生活習慣の見直しによってEDの症状が和らぐ場合もありますが、EDが自然に治るケースは限られています。
軽度のEDであれば、生活習慣の改善によって症状が改善する場合もありますが、「生活習慣を整えても変化を感じない」と感じる状態では、身体的な原因と心理的な原因が複雑化している可能性もあります。
EDの原因が複数ある場合、自分だけで改善を試みても、かえって悩みが長期化してしまうかもしれません。
生活習慣の改善はED対策としては必要ですが、それだけでは不十分であるケースも多いです。
EDの症状が軽度のうちに専門クリニックや主治医へ相談し、原因に合った対策を整理することが、効率の良いED治療に繋がります。
EDの治し方については、以下の記事でも詳しく説明しています。より詳しくEDの治療方法について知りたい人は、以下の記事もご確認ください。
EDになりやすい人に当てはまったら早めの対策が重要
EDは生活習慣の乱れやストレス、持病、服用中の薬剤など、複数の要因が重なって起こりやすい症状です。
まずは自分がEDになりやすい状態に当てはまっていないかを整理し、運動・食事・禁煙・適正飲酒・睡眠といった生活習慣の見直しや、ストレスを軽減する工夫から取り組むことで、予防や軽度の改善が期待できます。
心因性の要素が強い場合は、性に対する不安やプレッシャーを減らし、パートナーとのコミュニケーションや環境を整えることも有効です。
一方で、糖尿病や高血圧などの持病がある方や、持病の治療薬の影響が考えられる場合は、自己判断を避け、主治医や泌尿器科に相談することが欠かせません。
自分がEDかどうか気になる方は、早めに医療機関を受診することをおすすめします。


